詩人、作家、翻訳家として多くの著作がある木島始は、1957年、「大人の童話」として原作の「ニホンザル・スキトオリメ」を執筆。以降晩年に至るまで、童話のかたちのまま2002年までに5回にわたり自著に再録しました(木島は2004年没)。さらに、間宮の依頼で自ら書きおろしたオペラ台本のかたちでも自著に2度再録しています。他の著作(評論集、エッセイ集)や講演等でも、たびたび言及しています。
木島始が舞台初演(1966/3/14)公演プログラムに寄せた文章は こちら
原作童話『ニホンザル・スキトオリメ』をめぐって
初出
◆ニホンザル・スキトオリメ
~新日本文学会編『新日本文学』12巻12号(新日本文学会,1957年12月)p.61~67
再録(計5回)
◆童話 ニホンザル・スキトオリメ――動画のために――
~『ペタルの魂:木島始詩集』(飯塚書店,1960年11月)p.84~105
◆ニホンザル・スキトオリメ――絵のかきかたと森の火事の話――
~木島始 著, 池田竜雄 絵『ぼくらのペガサス』(理論社,1966年2月)p.60~86
※前文として「(キャッキャッキャーッというのを人間語にまとめてみたら、こんなものがたりになりました。休けいちゅうのお話です。)」という一文が付け加えられた
※末尾に「(これで、絵かきのサルのお話は、ひとまず、おしまい。)」と追加された
※作品の主題が最後の一文(「ホラアナや木の切株のなかのかたちに、ふと、何かいうにいわれないものを感じて、生きるこころと死ぬこころとのたたかいを、見てくれれば、それだけで、もういいのです。」)でより明確に表現されるなど、後半の細部の言い回しに(「大人の童話」でなく)本来の「童話」として読まれることを想定したと思われる変更がある。
※「あとがき」で木島自身がオペラ化について次のとおり言及している。
「ふしぎな絵やもようを見たら、サルの話を……(おもいだしてくれるかしら…)(この話をかきかえたものを間宮芳生さんが、すばらしいオペラに作曲してくれました。)…」
◆ニホンザル・スキトオリメ――絵のかきかたと森の火事の話――
~木島始 著『跳ぶもの匍うもの:木島始短篇集』(晶文社,1969年)p.189~206
 ※本文は理論社版と同一。
※本文は理論社版と同一。
※「あとがき」で木島自身が次のとおり言及している。
「『ニホンザル・スキトオリメ』は、大人の童話とわたしが呼んでいる作品のひとつで、間宮芳生の依頼でオペラ台本に書き直した。アン・ヘリングさんによって英語に、イヴァン・クロウスキー氏によってチェコ語に訳された。オペラ台本は『列島綺想曲』(法政大学出版局)に収めてある。」
◆ニホンザル・スキトオリメ
~木島始 著『ともかく道づれ』(青土社,1988年7月)p.238〜p.259
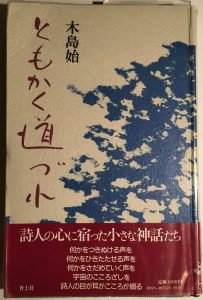 ※「あとがき」で木島自身が次のとおり言及している。
※「あとがき」で木島自身が次のとおり言及している。
「また一篇だけ『ニホンザル・スキトオリメ』は、第一短篇集にも入れた古い作品である。大人の童話とでも呼びたい作品の並んでいるなかに再登場させたわけは、これを脚色したオペラ台本(間宮芳生作曲)が思潮社版『木島始詩集』に収録してあって、原作はどういうものですかという質問に、ときどき出会すことがあるからである。(中略)
ふたたび誕生することをえたこれらの短い作品群の軌跡を、可能なかぎり見まもっていきたい。
本にもまた鬼籍あり
それは読まれぬこと
本にもまた奇蹟あり
それは縁むすぶこと
著者
一九八八年七月」
◆ニホンザル・スキトオリメ
~木島始 著『ともかく道づれ』(創風社,2002年6月)p.141~p.164
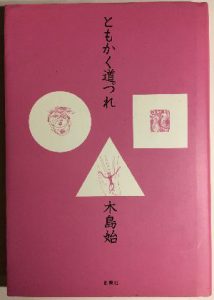 〔注:木島始には同じ書名で出版社・内容の異なる著書が『ともかく道づれ』以外にも存在する〕
〔注:木島始には同じ書名で出版社・内容の異なる著書が『ともかく道づれ』以外にも存在する〕
※「あとがき」で木島自身が次のとおり言及している。
「この『ともかく道づれ』は、一九八八年に青土社から出した本と同じ題名になっていますが、構成は、かなり変っています。
(中略)
そういう二一世紀に入ってからの新しいものにたいし、いちばん古い『ニホンザル・スキトオリメ』は、一九五七年生れですから、親子以上の年齢差があります。この作品は、イワン・クロウスキー氏のチェコ語訳、アン・ヘリングさんの英語訳があり、後者は”Ten Tales”(透土社)で読むことができます。また、間宮芳生作曲のオペラとして上演されるさい、オペラ台本に書きなおしたのを『木島始詩集』に収めていますので、読みくらべてもらうことも可能です。実在の日本猿は、決して尻尾がふさふさした美しさをもっていることはありえないので、このニホンザルは、あくまで架空なのですが、同じほど架空性がはっきりしていても、オペラ『ニホンザル・スキトオリメ』は、一九六六年の初演いらい舞台空間でふたたび表現されるまでに至っていません。もしかしたらその再演は、日本社会の表現の自由度の深化と関係があるかもしれない、とわたし個人は考えています。」
オペラ台本『ニホンザル・スキトオリメ』をめぐって
初出
◆オペラ台本『ニホンザル・スキトオリメ』
~20世紀文学研究会編『20世紀文学』第4号 特集:ドラマ(南雲堂,1966年4月)p.4~18
 ※木島自身によるあとがきと思われる文章2点(署名なし)が掲載されている。
※木島自身によるあとがきと思われる文章2点(署名なし)が掲載されている。
「この作品は、とくに子供のために書いたものではないけれども、理解されるところもあろうかと考え、脚色前の散文のかたちを、童話『ぼくらのペガサス』(理論社刊)に収めてある」
(「編集後記」)「四号の特集・ドラマは、最近とみに文学全般のなかで脚光を浴びつつある舞台芸術への照明を意図している。文学における言葉が、単に印刷としてでなく肉体からの発声として捉えなおされるとき、文学芸術は、新たな視角から検討されることが可能であろう。それは、小説でのフィクションに対する、仮面や演技の問題をもはらんでくる。今号に載せた脚本を上演したいむきがあれば、便宜をはかりたい。(K)」
再録(2回)
◆『ニホンザル・スキトオリメ』オペラ台本
~木島始 著『列島綺想曲』(法政大学出版局,1969)p.315~340
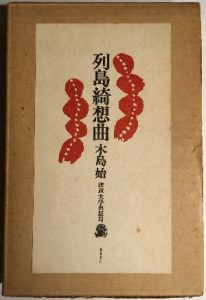 ※オペラ台本の前に3ページの「まえおき―――プログラムの小文」が置かれている。この「まえおき」は「1」と「2」という2つの部分で構成され、「1」はこの再録にあたり書き加えられたと思われる文章で、「2」は舞台初演の公演プログラムに寄せた文章(「初心の探求」)とほぼ同一である。
※オペラ台本の前に3ページの「まえおき―――プログラムの小文」が置かれている。この「まえおき」は「1」と「2」という2つの部分で構成され、「1」はこの再録にあたり書き加えられたと思われる文章で、「2」は舞台初演の公演プログラムに寄せた文章(「初心の探求」)とほぼ同一である。
※木島は、下記の「あとがき」で言及しているとおり、この物語の舞台を日本列島に「はっきりと限定」していた。これに対し間宮芳生は、「足の裏の音楽」(間宮芳生著「現代音楽の冒険」岩波新書,1990)文中にあるとおり「この物語が中世の十字軍の闘い、あるいはヨーロッパの宗教戦争のようなイメージを抱かせる」として、古楽器およびルネッサンス風の音楽様式を用いており、興味深い対照をなしている。のちに木島は「かれの読みの深さは、原作者のわたし以上であったと言えるかもしれない」(「群鳥の木」木島始エッセイ集, 創樹社, 1989)と述懐しており、間宮独自の発想を新鮮な思いで見守ったことが想像される。
「あとがき」より「これは、変幻とらえようのないわたしじしん、その体験と想像、その関心のありようを捕獲してみようとの軌跡です。(中略)
ただひとつ、この本のなかでの私の空想の舞台は、はっきりとした限定があります。つまり、アジアの東の端にあるひとつの火山列島です。この本に『列島綺想曲』という題をつけた理由には、しかし、もうひとつささやかなことですが、わたしが詩誌《列島》の同人だったという事実もあると、つけくわえておこうかと思います。綺想曲というのは、カプリチオ、つまり形式の制約のない音楽作品につかわれるイタリア語からきた言葉ですが、この本のように評論や戯曲や戯文や絵本やなどをつらねていく前例のない構成にたいしては、いささか音楽的すぎるとはいうものの、名づけかたとしては適当でないかと思っています。気どりついでに気どってしまえば、『列島綺想曲』とは、カプリチオ・ジャポネーゼCapricchio giapponese とい うことになります。(中略)
Iには、詩と戦争体験にふれての文章を収めました。他にわたしは「死の蛆」という短篇小説が原爆被災についてはあるきりで、この主題にはまだ直接ふれえないでいます。(中略)
VIIには、上演台本を二つ収めました。(中略)
「ニホンザル・スキトオリメ」は、最初ラジオで放送され、後に日本放送協会の創作歌劇の夕に東京文化会館で上演されました。
作曲・間宮芳生、指揮・若杉弘、演出・遠藤利男、美術原案・矢野真、音楽・NHK交響楽団です。配役は次のとおりでした。(中略)
このオペラ台本の最後が、ニホンザルの森が炎につつまれる場景ですので、この本全体は炎にはじまり、炎におわることになりました。もしかしたら、変幻きわまりない大きな炎が、わたしの綺想を見えないところから動かしているのかもしれません。
一九六九年秋
木島始」
◆オペラ台本『ニホンザル・スキトオリメ』-間宮芳生作曲-
~『木島始詩集』(現代詩文庫 53)(思潮社,1972)p.105~122 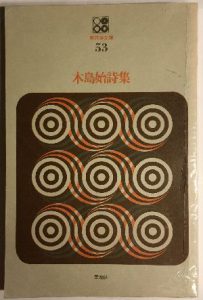
オペラ台本「ニホンザル・スキトオリメ」全文をお読みになりたいかたは
こちら↓
オペラ台本「ニホンザル・スキトオリメ」木島始 作

